| [トップ] [戦略] [日記] [読書] [討論] [蜘蛛] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略鍋:情報〜中小企業診断士の偏見的戦略論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報の共有化とは? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○広義の情報の共有化 会議、朝礼、人事異動による交流などを通して、広く会社情報の共有をはか ること。情報の共有化というより、共通認識を育てるという意味に近い。 ○狭義の情報の共有化 現実には、広義と狭義を区分けしてる人は少ないようで、共有化が重要重要 と叫んだあげく、会議を増やすことに注力し仕事に滞りがおきるなんてことが ある。こんなとき、会議の質が悪いと最悪である。イヤになります。ちなみに 私の勤める会社がそうである。 ○情報の共有化はなぜ大事? 会社にある「情報資源を有効利用するため」に必要である。 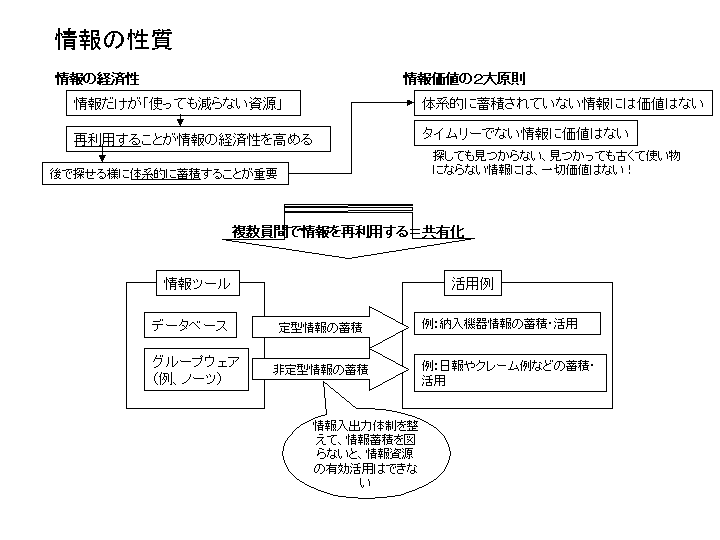
情報の共有化に関する基礎的な考えは、この表に全て盛り込まれています。 1.タイムリーでない情報には価値はない→即時入力の重要性 というわけで、即時入力の体制を整える、標準化・システム化する ことは 共有化以前に大変重要なことである。 ○共有化までのステップ ○共有化達成のためのデータ環境整備 収 集→情報リテラシの向上 ○共有化達成のための活用環境整備 データを整理整頓して蓄積し、ユーザーの情報リテラシ向上、パソコンの配置 をおこなっても、それだけでは「誰でも、いつでも、どこででも、同じもの」という 状態は達成されない。この4要素を満たすためには… ネットワーキング これが必要である。共有化すべきデータ環境を整え、ネットワークで接続することで 4要素は達成される。 ○共有化のキーワード 標準化・システム化、情報リテラシ、パソコンリテラシ、台数、能力、イン ターフェイス、ネットワーク をチェックする必要がある。 ○具体的な共有化達成ツール RDB:定型情報の共有化 と区分することができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ページの先頭] [トップ] [戦略] [日記] [読書] [討論] [蜘蛛] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営情報システムの発展経緯(MIS→DSS→SIS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.基礎概念:意思決定について
サイモンの意思決定理論はあまりに有名だが、この分類は現実的ではないとされている。なぜなら、日常の意思決定は構造/非構造と明確に分類できることはほとんどありえず、半構造的意思決定が多くを占めるといわれているからだ。 そもそも情報システムを語るには意思決定をまず知るべきである。情報処理と意思決定は、ほとんど同じ意味だといってよい。情報を処理するとは絶え間ない意思決定を経て行われることであり、意思決定とは絶え間なく情報を取捨選択しながら行われるからだ。 2.MISとDSSの比較 1)歴史的流れ 1962 ギャラガー 「MISアプローチ」 MISとは:企業の情報をデータバンクとして貯蔵しておき、各階層の情報利用者は欲しい時に欲する場所に居て欲する情報を手に入れる事が出来るシステム 1970 MIS失敗! ギャラガーのMISという考え方の問題点 ・必要な情報はあらかじめ意思決定者が熟知してるという仮定に立っている。 ・意思決定者の要求する情報を提供すれば意思決定が改善されるという仮定に立っている。 全ての情報をDBに貯蔵する事は技術的にも経済的にも不可能である。またトップは詳細データは通常必要としていないため、本来その必然性もない。加えて、トップが必要とする情報は、統括的・例外的・単発的・外部的なものである。このような情報を用いての意思決定においては、トップ自身どのような情報が必要であるか事前に予想することができない。そのため、情報を予めDBに貯蔵しておく事はやっぱり事実上不可能となる。こうして、結局経営者の意思決定には大きくは貢献できなかったのである。 そうはいっても、当初の目的は果たせなかったものの、「定型的、ルーチン的業務処理の合理化」にはMISは成功しており、一定の成果をあげることができたといえよう。 1978 キーン&スコットモートン DSS提唱 DSSの特性 ・半構造的意思決定を支援 ・管理場の判断を代替(REPLACE)するのではなく支援(SUPPORT)する ・意思決定の能率性(EFFICIENCY)を向上するのではなく有効性(EFFECTIVENESS)を向上させる ・データベース、モデルベース、ユーザーインターフェイスから構成される ・意思決定者とコンピュータが対話的な相互作用により意思決定を遂行する MISの失敗をうけ、DSSが提唱された。根底にあるのは意思決定者へのサポート、という考え方である。コンピュータがあれば意思決定までもが自動化できるという考えは、こうして修正されることとなる。 2)MISとDSSの比較 ここで一度、MISとDSSを比較としてまとめておこう
3.ES、インテリジェンスDSS、SISの登場 1985 ES(エキスパート・システム) ・最高の解を導くにはあまりにも論理が複雑な問題に対して、人間的推論を採用して「良い解」を導こうとするもの(非定型的意思決定支援) (MIS、DSSまでは定量的情報を分析的に扱うが、ESは定性的情報も扱おうとした。) しかし! ESが適用できるのは狭い範囲に限定された特定の意思決定のみとなってしまった。企業経営全般に関わる膨大な複雑な論理構造をプログラム化する事は、実際上不可能だったためである。 ?年 ES+DSS=インテリジェンスDSS ・データベース、モデルベース、ユーザーインターフェイスなどにESを組合せる事で、非定型的意思決定を支援できるように工夫する案が生まれた。これがIDSSとなる。 1985(ESと同時期) ハーバード大より戦略的武器としての情報システムという概念が発生=SIS ・SISの目的 競争優位を獲得維持するために意図的・合理的に構築される情報システムのことである。MIS、DSSは意思決定という概念的パースペクティブ、SISは競争優位という戦略的なパースペクティブ という違いがある 承知のとおり、情報システムはまだまだ急速に発展し姿を変えていっているものである。人間の脳を目指すコンピュータ発展の勢いは加速するばかりであるが、やはりしょせんは道具である、という認識が重要であろう。特に、昨今の暗黙知といった考え方を考慮すると、人間にしかできない領域はまだまだ広い。 (2001年11月24日 土曜日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ページの先頭] [トップ] [戦略] [日記] [読書] [討論] [蜘蛛] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||